
TEAMWORK
コミュニケーションで築く、
支え合いと助け合いが根付く現場。
- 保育士
- 児童指導員
- 栄養士
- 調理師


ワークとライフ。
どちらも充実できる働き方へ。
1日の全てが仕事ばかりではむなしく、プライベートばかりが楽しみな1日もどこか張り合いがありません。ワークとライフ、人生の充実にはどちらも欠かせない存在です。ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、ソシオークグループで働く社員たちはどんな工夫をしているのでしょうか。3名の社員が、仕事とプライベートについて語り合いました。

2013年に総合職として新卒入社。首都圏内にある学校給食の事業所を運営する部署の部長として、事業所の運営支援や自治体・学校との調整、人財採用などを担う。一児の父。

2020年に新卒入社。学生時代にあしたばマインドが運営する保育園でアルバイトをしており、卒業後に正社員として入社。保育士として、0歳、1歳、2歳、4歳、5歳の担任を歴任している。

インターンシップの参加がきっかけとなり2016年に明日葉に新卒入社。学童保育を担う児童指導員の職に就く。現在は東京の小学校にて、200名近い児童が通う学童の運営に携わっている。一児の母。

給食事業を運営する葉隠勇進に総合職として入社してから、現場社員が活躍できるように事業所の運営支援を担っています。活用している制度でいえば、変形労働制がとても役立っています。変形労働制は簡単にいうと固定された勤務時間ではなく、決められた条件の中で始業や終業時刻をシフトを組んで働く制度です。給食の現場は、朝の6時から稼働しているところもあります。事業所巡回時は早朝に出勤して、午後早めに退勤するシフトにするなど、様々な勤務時間のシフトを組んで働くことができています。
また、テレワークも週1〜3日ほど活用しています。午前中に自宅で仕事をして、午後の会議のために出社するときなどは、満員電車もないので快適に通勤できるのがありがたいです。

私は保育士として5才児の担任をしています。働いている保育園では体制表を導入していて、効率的な業務につながっていると感じます。体制表には、こどもの名前や登園時間、職員の名前や出勤/休憩時間などが記載されています。大まかではありますが、どこで、誰が、何をしているのかを把握することができるんです。
例えば、こどもたちに紙でひまわりをつくってもらう時間が控えているとします。こどもたちが紙をひまわりのカタチに切りやすいように、事前にひまわりの下絵を書いておく準備が必要な場合、体制表を見ながら比較的、手が空いている先生に協力をお願いするんです。体制表を見れば、この時間、誰がなにをしているのかを大体把握できるので、残業することなく勤務時間内で作業を終えられるという点において、とても役立ちます。

小学校にある学童で、放課後や夏休みなど長期休暇中のこどもを見守る児童指導員として働いています。勤務体系には早番と遅番があり、現在は早番の固定勤務にしてもらっています。また、早番の勤務時間は通常9:30〜18:30なんですが、私は9:15〜18:15で働いています。というのも、子育ての真っ最中で保育園への迎えが18:30終業だと厳しく、そのことを責任者の方に相談したら時間を調整していただくことができました。制度の活用とは異なるかもしれませんが、ワーク・ライフ・バランスに向けて柔軟に対応してもらえるのがありがたいですね。
あとは、産前産後休暇や育児休暇も取得していて、こどもが3歳になるまでは時短勤務制度も活用していました。

私のいる保育園でも第一子出産時に産育休を取得し、復帰後は時短勤務制度を活用して働き、第二子にも同様に制度を活用している先生がいます。この保育園に復帰したい。復帰しやすいと思える環境です。

本社社員も女性はもちろん、男性の育休取得者が増えています。今度、育休に入る責任者が2名いるのですが、どちらも男性社員ですね。


退勤後、予定を入れていない日は疲れを取るためによく寝ます!早番のときには16時に終わるので、友達と遊んだりしてリフレッシュしていますね。

住んでいる場所から実家が徒歩5分圏内にあるため、「たまには羽を伸ばしたい!」というときには、こどもを実家に預けて家でゆっくり過ごしています。また、義実家がこどもを水族館や動物園などアクティブにいろんな場所に連れて行ってくれるなど、実家と義実家にたくさん頼りながらプライベートを満喫しています。

日にもよりますが、もっぱら家族と過ごすことがほとんどです。平日は仕事終わりに2歳のこどものお迎えに行ってご飯を食べて一緒にお風呂に入ったり、休日はちょっと遠出して遊んだりと、こども中心の生活を送っています。あと、急に熱を出したこどもを病院に連れていかないといけないときなどは、有給を利用することも多いです。

推しのライブに行くときなどには、私も有給を使うときがあります。数ヶ月分の仮シフト表があって、他の先生と休みが被らないようにすれば、「楽しんでおいで〜」という感じで有給は取りやすいです。

有給については申請すれば通りますし、むしろシフトを組んでいる責任者が「この日は有給とれそうだけど、どう?」という感じで、積極的に有給取得を提案してくれます。


性格上、ミスを勤務終了後も引きずることがあります。ミスを次に活かすために反省は必要ですが、不安が抜けないとプライベートで気が休まらないので、オンとオフをしっかり分けて、オフに仕事を持ち越さないように意識しています。
また、残業する場合には園長先生に事前申請する必要があるのですが、申請したら園長先生から「勤務時間内にできるように、次の日のこの時間を空けるよ」といった感じで調整してくださることもあります。そのためほとんど残業することなく働けています。

私も家庭との両立を考えて残業はしないようにはしています。特別に意識していることではありませんが、できることは早めに済ませる、引き継げる業務はメンバーにお願いするなどですね。

がむしゃらに働いていた新人時代と比べると、私も効率性を意識するようになりました。働き方を見直したきっかけは、こどもの存在が大きいです。こどもが生まれる前までは「どんな時間も仕事だから対応しなくちゃいけない」「責任を持って自分がやらなくちゃいけない」、そんな考えを持っていました。でも、子育てするようになって、今まで通りの働き方では到底両立できないことが分かったんです。
責任感を持つことは大切です。でも、自分一人で働いているわけではありませんから。「周囲を頼る」ということを覚えました。仕事のタスクを整理して自分でなくてもいいものは他の人にお願いしたり、自分が稼働している時間を周囲に知らせておいて、必要な報告をその時間帯にしてもらうようにしたり。時間を意識して働くようになってから残業は減りましたが、生産性は逆に上がったように思います。

どうしても自分が対応しなければならない仕事は仕方がないですが、冷静になって考えてみると自分じゃないとダメなことって意外と多くありません。ワーク・ライフ・バランスの実現するためには周囲との協力関係は欠かせないので、普段からコミュニケーションをたくさん取って、お互いに頼みやすい関係をつくっておくことは大切ですね。

とても大切だと思います。うちの保育園でも体調を崩して急きょ病院に行かないといけないときなどは、他の先生と声を掛け合いながらシフトを変更するなどして対応しています。

仕事をしていると、どうしても一人で抱え込んでしまう瞬間はあります。部下や後輩がそうなった場合はまず話を聞いて、チームで対応するようにしています。自分もこれまで他のメンバーから支えてもらってきたことも振り返ると、会社自体に支え合いの風土が根付いているように感じています。

支え合いで言えば、育休明けの職場復帰時には、復帰前から上司とメールや電話で何度も連絡を取り合っていました。時短勤務として何時まで働けるか、事務作業をどう分担するかなど事前に話し合えたので、安心して復帰することができました。こどもを見守るという仕事上、周囲のメンバーも育児への理解が高く、たくさんの配慮をいただいた結果、時短中も無理なく働くことができました。


仕事で忙殺されると、楽しいことも見逃しがちになります。気持ちに余裕を持てる働き方を実現して、日々のこどもたちの成長を存分に喜べるようにしたいです。保育の仕事をして感じるのは、行事の存在ってとても大きいんです。担任していたクラスで、カラフルな大きい布をこどもたちで持って表現を楽しむ、パラバルーンを行事で発表する機会がありました。発表に向けて、みんな一生懸命練習するんですね。その姿を見ていたので、本番の演技中に思わず泣いてしまいまして。そのときに駆け寄ってくれたこどもたちの優しさがまたうれしくて。この仕事をやっていてよかったなと思う瞬間でした。そんなかけがえなのない、そのときにしか味わえない瞬間を見逃さないためにも、プライベートを充実させて心に余裕をもって、仕事も存分に楽しめる自分でいたいです。

時々、自分の一言でこどもが見違えるように大きく成長することがあります。私もその瞬間に一度でも多く出会うために、長く働き続けたいです。学童での仕事は、こどもたちにいろいろと教えているようで、教えられることもたくさんあります。見守っている、指導しているというより、指導力を試されているという感覚のほうが近いです。試行錯誤の日々を続けるためにも、今のように仕事にも熱意を傾けられる働き方を続けたいです。

スキルだけじゃなく前向きな気持ちも、仕事を長く続けるうえでは大切ですよね。残業を減らして、こどもの成長を見守る時間が増えるようになって、心の余裕ができたと思います。心の余裕は、新しいことを始める余白になります。その余白を活かして、メンバーにもいろんなチャレンジをしてほしいと思っています。自分自身、マネジメント職に就いたとき、その先のキャリアが漠然としていたんです。そのときの上司からアドバイスを受け、人財採用活動などいろんな新しい業務にチャレンジさせてもらってキャリアが広がったように思います。
そのため、メンバー全員のワーク・ライフ・バランスを充実させて、眼の前の仕事に追われるのではなく、自分のなりたい姿を追いかけられるようにして、彼らのキャリア形成をサポートしていきたいです。


コミュニケーションで築く、
支え合いと助け合いが根付く現場。

ワークとライフ。
どちらも充実できる働き方へ。

「現場力」こそ、
やりがいと喜びを生みだす原動力
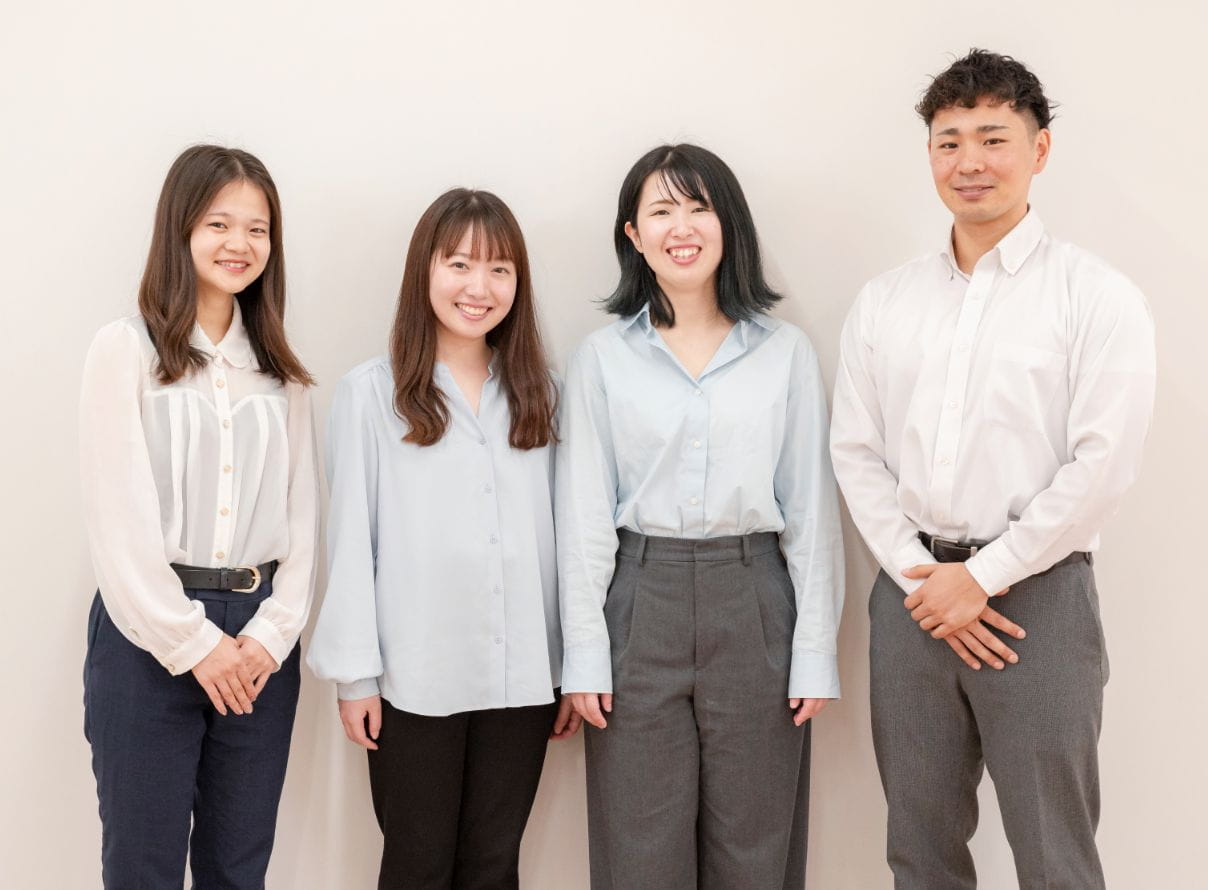
自身の行動が、
1人の人生を変える。
社会への影響力を感じた仕事。

進化の意識とグループの力で
社会課題の解決を応えていく

どれほど時代が進歩しても、
未来を創るのは技術より人の想い

社会に役立ち、必要とされる。
そんな働きがいあるビジネスを、次々と。